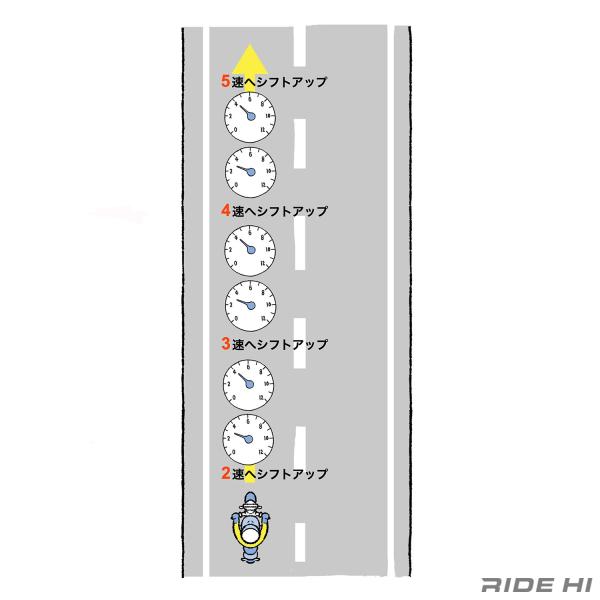ヤマハがパフォーマンスと洗練さでエンスー向けシングルを開発
開発エンジニアもデザイナーもこだわり派揃い、妥協を許さない大人の感性で突き抜けた完成度を誇った
空冷シングル(単気筒)スポーツといえば、SR400に代表されるクラシカルなバイクをイメージするかも知れない。
しかし’80年代後半には、シングルでも原点復帰を楽しむのではなく、スポーツライディングでツインや4気筒を追いかけ回し抜き去る……そんな硬派な路線を目指したバイクが人気を集めた。
ヤマハSRX400/600、人気車種で生産台数も多かったことから、いまもそのハンドリングを楽しむファンに愛されている名車だ。
そもそものきっかけは、1978年に発売開始となったSR400/500の後継機種の開発がスタートだった。
お気楽な風潮に喝を入れるエンスーコンセプト
しかし、性能を追わないクラシカルな佇まいのSRは確かに人気を得たが、時代はスーパースポーツの開発競争の渦中で、新しいメカニズムや素材などが毎年投入されるNewモデルラッシュ。
バイクブームということもあって、女性を意識したスポーツバイクも加わり、世相と共に「もっと気楽に行こうぜ」的な価値観で“本モノ”を求めない風潮に、このSRX開発チームはアンチお気楽をスローガンに、エンスージアスト路線を突っ走ることになったのだ。
もとより開発エンジニアは、自分で分解組み立てなど朝飯前のエンスー揃い。性能はもちろん、持ち物には趣味人としてのこだわりは必須と、大量生産で中庸が主流の日本メーカーには珍しいコンセプトが貫かれた。


エキパイの焼け色がファンの心を掴む
エンジンはオフ系シングルがベースだが、そのチューンに力強さと洗練されたフィーリングが込められ、オフ系のエンジン下にオイル溜めを持たないため、オイルタンクをエンジン後部にマウント、エンジン下のスペースへ最新スーパーバイクでお馴染みの排気チャンバーを格納して、長いサイレンサーが常識の時代にショートマフラーを実現したのだ。
さらにツインポートから出る2本のエキゾーストは、量産車では初のステンレス製で焼け色を楽しませるというエンスーならではのつくり。
フレームも当時の世界GPワークスマシンだけが採用していた角断面パイプによるダブルクレードルとトップクラス仕様が奢られていた。
そしてデザインはヤマハを世界で再認識させたVmaxを手掛けたこれも超のつくこだわり派。
スリムさにこだわり、局面に膨らみだけでなく凹みも活用するなど、まさに新時代を予感させるレベルへとまとめ上げたのだ。
サイドのアルミカバーは、当時ほとんどが樹脂製へ塗装加工が主流な頃に、エンスーには本モノでなければと妥協を許さない意地の塊だった。


完璧なコーナリングマナーで絶品ハンドリング
このアンチお気楽のエンスー揃いが開発しただけに、SRX400/600は走りもすべてが高次元でバランスする、弱点を捜そうにも完璧すぎて誰が乗っても自分のアベレージをふた回りほど高める傑作マシンに仕上がっていた。
1985年にデビューした後も、18インチ時代からフロント17インチ時代への移行期で走りにこだわるマイナーチェンジを挟み、5年後には同じコンセプトでさらに高みを目指したフルモデルチェンジを敢行。
おそらくこのあたりは、いまも多くいるSRXファンが好みを分けるところだろうが、最終型での進化の著しさは評価的にも他を圧倒する高次元なまとまりをみせていた。
エレガントさから逞しさが加味された新時代を予感させるデザインは、いまでも通用する斬新さで圧倒的な魅力を放つ。
パフォーマンスもエンジン前方へ持ってきたオイルタンクで冷却性を向上、リヤのモノサス化で路面に吸い付くようなプログレッシブ特性と、前後17インチの完全ラジアル化も加わって、大型スーパースポーツよりコーナリングスピードも高く、さらに完璧なバランスで驚愕の旋回安定性を誇ったのだ。
その後、フルカウルのスーパースポーツとビッグネイキッドなど、繊細さに心を動かされるシングルに活躍の舞台は与えられないまま。
ただ最近マイノリティで多様化してきた中、こうしたスポーティな感性をターゲットにしたNewコンセプトが生まれるチャンスはあるに違いない。